バイオマスプラスチックといった自然に還る素材を、使用したエコな器をご紹介します。
更新日:2020年03月29日

自然に還るエコな食器をご紹介します。
ゴミ問題を解決する上で重要な、土に還るエコな食器をご紹介します。自然に還るエコな食器に着眼したのは、ゴミの問題がコストの問題と同列に扱われると思うからです。ゴミというのは、処分するために大変なコストがかかります。しかし、それを見ないふりをしてやり過ごすことも多い問題です。ゴミの問題を先送りしていると、将来的にその悪い部分が降りかかってきます。生ごみは自然に帰るということをイメージできます。生ごみであればゴミの自給自足が可能です。ただ、現在の生活では、プラスチックのトレーなど、生ごみでないものが生活において多くのウェイトを占めています。ゴミも自給自足するにあたっては、できるだけ生ごみだけにまとめなければいけません。生ごみは堆肥にもなりますし、循環する有機物です。しかしプラスチックなどの不燃ゴミは、循環しないので埋め立てて処分する形になります。不燃ゴミが多くなるとリサイクルをしなければいけませんが、リサイクルをするためには効率的な処理が必要になります。ゴミの分別をシンプルにするためにも、ほとんどのものを生ごみにして自分のところで処分してしまい、それ以外のものをリサイクルに回すのが、ゴミ問題をシンプルにしてコストをかけずに、ロハスな生活になると考えます。そこで、ゴミももっと自給自足で生ごみと同じように処分、解決してしまおうという発想から、自然に還るエコな食器という考え方が必要になってきます。トレーなどのプラスチックで代用しているものを、自然に還るエコなものに変えてしまいたいと思います。食器という言い方をしましたが、トレーでも良いですし、土に還るエコなトレーという意味で、土に還る食器と言っています。それらを土に埋めれば、微生物が分解して土に還るため、自治体で処分する費用も大きく下がります。さらに、どこでもゴミを処分できるようになります。いちばん大きな壁は、コスト問題だと考えられます。普通のプラスチック製のものに比べて、新しい製品はコストがかかります。コストの問題をイノベーションで解決する必要があります。今回の問題の本質は、エコな食器ということではなく、ゴミ問題をいかに解決するかということです。そのために、自分のところでプラスチック製品を使用せず、土に還る食器のように生ごみとして処分できる商品を使うことが良いのではないかという発想です。それ以外にも、プラスチックを仮に燃やそうとすると、ダイオキシンなども発生します。生ごみの場合は、肥料として再利用も可能です。また、これまでの生活習慣を変えることなく、コストも変わらず、おしゃれにゴミと向き合えるということが大切だと考えます。コストの部分とともに、生活習慣を変えなければならないようだと、採用するハードルがとても上がってしまいます。それと、自然に還る食器にしてもそうですが、デザイン性といったおしゃれな要素がふんだんに取り入れられています。この部分は利用する商品を切り替える上で重要だと思います。さて、土に還る食器に関してですが、椰子の実や和紙などを使った本当に植物素材でできた食器がありますが、それはもちろん土に還ります。注目されているのは、植物由来のバイオマスで作った土に還るプラスチックとして有名な「バイオマスプラスチック」や「生分解性プラスチック」です。「バイオマスプラスチック」は、トウモロコシのデンプンなど、石油以外のものから作られているため、CO2が大気中に増えません。一方、「生分解性プラスチック」は、ゴミが微生物に分解されるときに発生するバイオガスからメタンを取り出し、燃料として使うこともできます。バイオマスプラスチックに利用されるデンプンから構成される「ポリ乳酸」のような、植物由来のプラスチックは、石油プラスチックの代替品として有望です。柔軟性や耐熱性に劣るといった問題があるので、その点を改善していかなければいけません。コストの面もまだ石油製品に比べて高価であったりと、工夫が必要です。バイオマスプラスチックで工業化されているのは、基本的にポリ乳酸しかありませんが、土に還るという特徴を生かすためにも、研究を進めていかなければいけない素材です。包装自体を簡素化するということも重要です。バイオマスプラスチックの原料ですが、「米の籾殻」や「竹の繊維」といった、食品と競合しない材料を使うことも重要です。今後のイノベーションに期待されます。
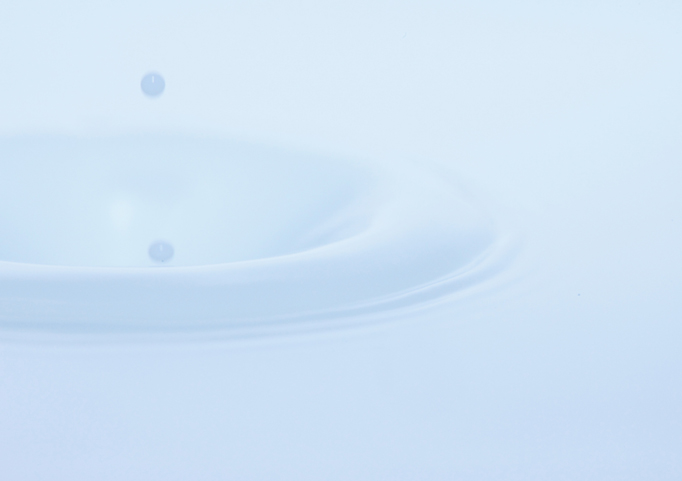
自然に還元するテクノロジーをご紹介します。
生活する上で必要となるプラスチックや、洗剤といった消耗品の未来のテクノロジーをご紹介します。
■生分解性プラスチック
生分解性プラスチックは、プラスチックでありながら微生物によって最終的に水と二酸化炭素に分解されるものです。環境負荷が低いプラスチックと言えます。生分解性プラスチックは、バイオマス由来の「植物系生分解性プラスチック(バイオプラスチック)」と石油由来の「石油系生分解性プラスチック」に分かれます。生分解性プラスチックは分解すればよいので、すべてが植物由来というわけではありません。植物系生分解性プラスチックには、トウモロコシでんぷんから作られるプラスチックなどもあります。また、生物が分解する際にバイオガスを発生させるため、それを燃料として利用することも可能です。木材パルプから作った生分解性プラスチックでは、土の中に埋めて半年以内に90%程度が分解したそうです。生態系への影響がないことも分かっており、とても有用なものと言えます。食物などの有機性廃棄物を堆肥化するための収集袋などは、そのまま埋められるため、生分解性の性質を発揮するのに適しており、環境負荷軽減に使える素材です。石油由来の生分解性プラスチックの代表的な素材としては、「PET共重合体」があります。
■バイオマスプラスチック
バイオマスプラスチックは、植物などが由来となったプラスチックです。「生分解するプラスチック」と「生分解しないプラスチック」に分かれます。生分解するバイオマス由来のプラスチックは、環境問題や資源枯渇の問題を考えると、とても将来性のあるプラスチックとして期待されています。植物に含まれるでんぷんを原料にしたバイオマスプラスチックは、植物が光合成で大気中の二酸化炭素を吸収して作られるため、利用後に燃やしても大気中の二酸化炭素が増えず、温暖化などの地球環境への負荷が少ないプラスチックと言えます。また、植物という再生可能な有機資源を使うため、石油のように枯渇が危惧されることはなく、持続的に生産できる将来性ある素材です。食物との競合を避けるため、竹などの非木材、非食品のものから作るのが望ましいと考えられています。生分解性のバイオマスプラスチックが発展し、コスト面をクリアすることで、現在私たちの生活に浸透しているリサイクルに依存しなければならない生分解しない石油系プラスチックから、肥料などにもなりうる地球環境に優しいプラスチックが生まれる可能性があります。でんぷんから合成される「ポリ乳酸」は、バイオマス由来の生分解性プラスチックとして有名です。それ以外にも、「ポリカプロラクトン」「ポリヒドロキシアルカノエート」「ポリグリコール酸」「変性ポリビニルアルコール」「カゼイン」「変性澱粉」があります。
■エコ洗剤
日常的に使う消耗品として、食器洗いや洗濯用の洗剤、体を洗うための石鹸などが挙げられます。これらは通常のものを使うと界面活性剤などが含まれており、環境負荷が高くなります。洗剤などの消耗品も、植物由来や生分解性のものを使うことで、環境負荷を下げることができます。代表的な洗剤には、ベルギー発祥のECOVER(エコベール)、ドイツ生まれのカエルのマークが特徴的な「フロッシュ」、ヤシノミ由来の植物性洗剤の「サラヤ」などがあります。生態系の面から見ると、生分解性の洗剤を使えば下水処理などの必要性が低減されます。浄化槽を使用する住宅では、生分解性洗剤を使った方が浄化槽の寿命延長にもつながります。このように洗剤に配慮することも、持続可能な生活を送る上で大切だと考えられます。
■油化
プラスチックは、基本的にリサイクルすることで再利用されますが、本来プラスチックは石油から作られているため、再度石油に戻すことも可能です。コスト面でのハードルは高いものの、廃棄されるプラスチックを石油として利用できるということは、利用用途が広がり、夢あるテクノロジーと言えます。
